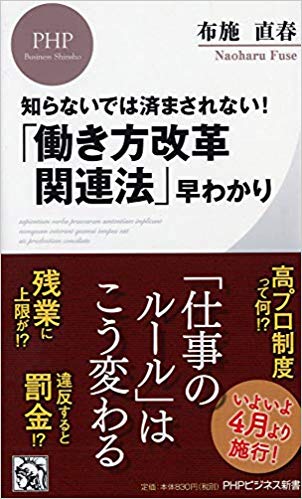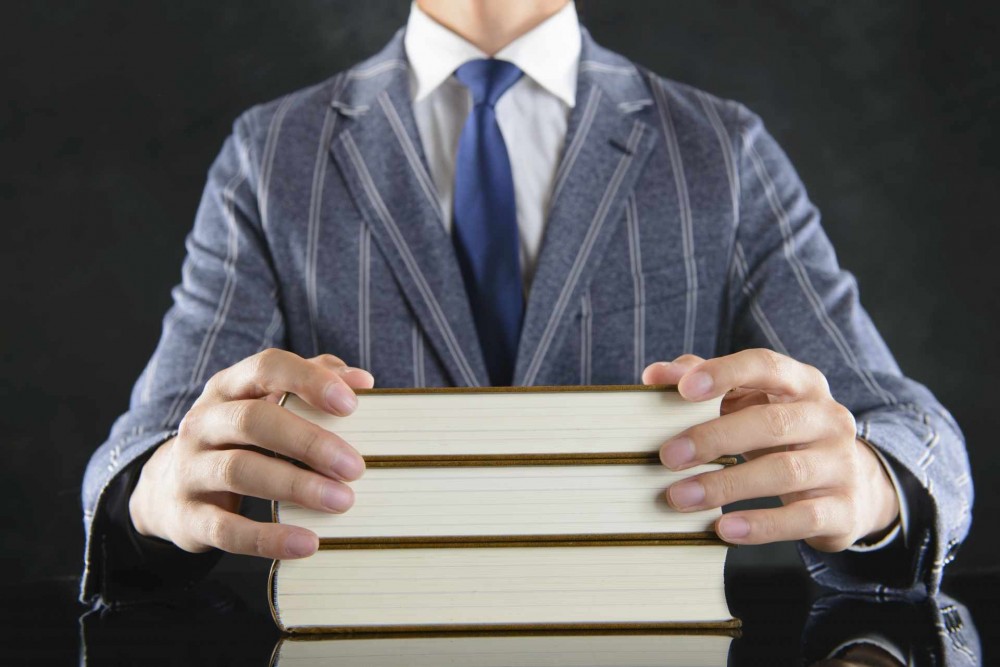「4月1日より、残業時間に上限が」……って、今まで残業に上限はなかったの?
2019年03月06日 公開
2024年12月16日 更新
「特別条項」が悪いわけではないのだが……
以上が労働基準法で定められた「労働時間」の基本ですが、決算前の忙しい時期や、思わぬ商品の大ヒットにより、その程度の残業ではとても追いつかない、というケースもあると思います。季節商品を扱っているため、ある時期に生産が集中するというケースもあるでしょう。
そういった特別な事情が予想される場合、36協定の中に「特別条項」を結ぶことで、定められた時間外労働の上限以上に働くことが可能になるのです。
そんな条項、労働者にとって不利なだけでは、と思うかもしれません。ただ、社員だって好景気のときにたくさん働けば会社の利益も増え、自分の給料にも反映されるかもしれません。また、会社のピンチの際、助けたいと思うのも当然でしょう。「特別条項」そのものは、うまく使えば労使ともにメリットのある制度と言えるのです。
青天井だった特別条項にもやっと「上限」が
ただ、問題はこの「特別条項」には、残業時間の上限がなかったということ。つまり、150時間残業させようが200時間残業させようが、いわゆる「青天井」(上限なし)だったわけです。
唯一あったのが「1年のうち通算6カ月にわたって、36協定の原則的な限度時間を超える時間外労働をさせることができる」、逆に言えば「7カ月以上にわたって限度時間を超えてはならない」という期間に関する条件だけで、肝心の時間外労働の時間数についての上限がありませんでした。
そのため、この特別条項の抜け道が青天井の残業の温床となってしまっていたという側面があるのです。また、「特別条項」さえ結んでおけばいい、という安易な考え方をする会社があったことも事実です。
そこで、今回の法改正では、「特別条項を結んだうえでの残業の上限」が決められることとなりました。具体的には以下となります。
A 時間外労働と休日労働の合計が、1カ月で100時間未満
B 時間外労働と休日労働の合計が、2~6カ月平均ですべて1月あたり80時間以内
C 時間外労働が、1年間で720時間以内
D 特別条項の適用は1年間に6カ月まで
この数字を多いと見るか妥当と見るかは人それぞれでしょう。
「時間外労働と休日労働の合計が、1カ月で100時間未満」「2~6カ月平均で80時間以内」というのは、労災保険給付の対象となる、いわゆる「過労死ライン」と一致します。会社が社員をこれ以上働かせると健康を害す恐れがあるという時間で、過労死や過労自殺の判定の際に、この数値が基準とされます。
ちなみに「特別条項」が必要ない場合でも、このルールが当てはまります。時間外労働は45時間で収まっていても、休日労働が56時間以上となると、合計は月100時間を超えてしまい、法違反となります。
つまり、特別条項があってもなくても、1年間を通して時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内というのがルールになった、ということなのです。
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月04日 00:05
- 血圧を下げる「カリウムが豊富な食材」とは? 高血圧専門医が解説
- 高血圧専門医が教える「ほんの少しの意識」で降圧が優位に進む2つの秘策
- 医師が語る、40代からの健康診断で必ずチェックすべき「4つの数値」
- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣
- グラウンドワークス「エヴァンゲリオンの版権ビジネスが成功し続けている理由」
- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い
- 血圧を下げるには減塩だけでは不十分? 医師が語る「カリウム摂取」の重要性
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 高血圧改善に必要な運動量は? 専門医が警告する「ハードな運動」のリスク
- 日本サッカーはなぜ「地域密着」なのか…23歳の川淵三郎が見たドイツの天然芝の衝撃