業務改善のためにまず何をする? 「取り組むべき課題」の絞り込み方
2025年08月22日 公開

今は、会社が部門や部署ごとに一律の目標を示せるような単純な時代ではありません。中期経営計画や戦略資料には抽象的な言葉が並び、各部署に「これに取り組め」と明示されることはほとんどありません。
だからこそ重要なのは、今後の自分たちはどうありたいかという現時点ではまだ「見えていない問題」や、お客様自身が認識していない潜在的な課題を解決することです。とはいえ、こうした問題は明確な形を持たないため、「本当に取り組むべきなのか」「どの課題を選ぶべきか」という判断が必要です。
本稿では、課題を絞り込む方法について書籍『課題解決の思考法 「見えていない問題」を発見するアプローチ』より解説します。
※本稿は、高松康平著『課題解決の思考法「見えていない問題」を発見するアプローチ』(日本実業出版社)より内容を一部抜粋・編集したものです
課題は選ぶもの

まず、「絶対的な課題」は存在するかどうかを考えていきましょう。「絶対的な課題」というのは、ほかに課題は存在せず、それだけが唯一無二の課題であるという意味です。
飛行機や鉄道などの事故の場合には「絶対的な課題」は存在することが多いです。
これまでは安全運転ができていたけれど、そのときだけ事故が発生してしまった。だから、そのときできていなかったことを直す。つまり、「絶対的な課題」が存在します。
では、一般的なビジネスの現場では「絶対的な課題」は存在するのでしょうか? 「売上を上げるための課題は?」「利益を増やすための課題は?」。こういった場合の課題は相対的な存在であると考えたほうが合理的でしょう。
とくに「見えていない問題」を発見する際には、この点を意識する必要があります。
「見えている問題」の場合は、問題が明確になっています。そのため、その問題がなぜ起きてしまったのかを探り、課題を明らかにします。
問題が起きた際、その問題が起きたのは、はじめてではないことも多いでしょう。過去に似たような問題が起きた際にも、対策が講じられたはずです。
でも、また問題が発生してしまった。「なぜ、その問題がまだ解決されていないのか(why not yet)」を考える必要があります。課題を明らかにする際には、「今回はなぜできていなかったのか」という原因となる事実を探します。
・本来はできているはずなのに、今回はなぜできていなかったのか?
・これまではできていたのに、なぜ今回はできなかったのか?
・対策を講じたのに、なぜ今回も問題が起きてしまったのか?
・競合はできているのに、なぜ自社はできていないのか?
これらの問いに答える強力な事実があれば、帰納的にまとめたとしても説得力があります。
一方で、「見えていない問題」の場合はどうでしょうか? 明確な問題が存在するわけではありません。このタイミングで、これが「絶対的な課題」だと言われても、説得力はありません。そもそも、何が問題なのかも決まっていないなかで、問題を解決する「絶対的な課題」を証明することはできません。「見えていない問題」の場合、「課題は相対的」なのです。
つまり、「なぜ、ほかの課題でないか(why not others)」を考える必要があるのです。ほかの課題に取り組むよりも、この課題に取り組むほうがより良い未来をつくることができることを証明しなければなりません。
だから、「これが課題です」と提案したにもかかわらず、上司は「ほかの課題はないのか」と質問をするのです。上司は自らの役割があるから質問するのであって、単純に性格が悪いからではないのです(性格が悪い人もいるかもしれませんが)。
では、「課題を選ぶ」ということはどういうことなのか。「課題を選ぶ」パターンは大きく3つあります。

①「どこを伸ばすのか」
結果分解された部分のどこを伸ばすのかを選びます。
たとえば、部分A、部分B、部分Cの中でどこを伸ばすのかを選びます。マーケティングの提案なら、「どのセグメントを伸ばすのか?」、業務改善で言えば、「どの領域を改善するのか」を選びます。
② 「何に取り組むのか」
何に取り組むのか、何に取り組まないのかを考えます。
たとえば、「認知度アップに取り組むのか?」「商品力を高めるのか?」、それとも「チャネル拡大に取り組むのか」などを選びます。
③ 「何を強化するか」
何を強化して、何を強化しないのかを選びます。
たとえば、チャネルを強化するためには「人の育成が必要なのか?」「お金が必要なのか?」「データが必要なのか?」など何を強化するのかを選びます。
課題を選ぶ際には、「どこを伸ばすのか」×「何に取り組むのか」×「何を強化するか」を複合的に考えるため、課題の選択肢は無数に存在します。その中で有力な課題の候補をリストアップして、一番効果的なものを課題として選びます。
何に取り組んだら、より良い未来をつくれるかという思考は、非常に楽しいものです。これからの作戦を決める一番のポイントであり、新しい未来をつくる前向きな時間です。
課題を議論する場をつくる
「課題を決める=取り組むことを絞る」わけですので、ここが最重要のポイントとなります。
課題を決めるタイミングで提案の方向性がほぼ決定しますので、ここで上司やお客様と議論する場をつくります。すぐに結論を出そうとせず、さまざまな観点から意見交換を行います。
議論をするためには、9枚の資料が必要です。
・最初の3枚で現状を理解する
① (結果評価)現状は......
② (結果分解)詳細に分解すると......
③ (原因分析)その理由は......
・次の3枚で新たな事実を発見する
④ (未来を想像)このままいくと......
⑤ (重要な事実)じつは、こういう事実がある
⑥ (ケリをつけたい質問 [AとB、どちらをすべきか決着をつけるための質問])どうすべきか検証してみた
※任意
・最後の3枚で課題を決める
⑦(帰納的まとめ)これまでの話を整理すると......
⑧(課題を決めるキーチャート)課題は〇〇となる
⑨(補足の事実)なぜならば~であるから
なぜ、このテーマに取り組むのかという説明が必要であれば、冒頭に⓪背景情報(テーマ設定の理由)を追加してください。
なお、⑥の「ケリをつけたい質問」は、具体的な仮説が明確にある場合は追加してほしいですが、必須ではありません。
資料を作成したら、チームで議論をします。
ここで大切なのは、自分の意見は明確にするものの、その意見に固執するのではなく、よい議論をすることです。
あくまで課題"案"です。ほかの課題に取り組むべきだという意見が出てきたら、なぜそう思ったのかを聞けばいいのです。資料には出てきていない、ほかの課題候補が出てくるかもしれません。
課題を決めるキーチャートにより、活発な議論が生まれます。
議論が盛り上がり収束できないこともあります。そんな場面が生まれたら、最高です。それだけ悩ましい意思決定に迫ることができたと言えます。
なお、これまでの世の中の多くの問題解決の研修においては、課題を「選ぶ」ということを教えていなかったように感じます。どんな施策をするかを選ぶよりも、どの課題に取り組むのかを選ぶほうが重要です。
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:10月29日 00:05
- 「資産1億円」では幸せになれない理由とは? 高年収を夢見る中学生が知った”お金の正体”
- 「55歳からの投資」 定年5年前に始めるべき3つの理由とは?
- BCGが目を付けた「利益度外視の日本企業」 世界を驚かせた低価格戦略の真実
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- 森永卓郎氏が警鐘を鳴らす「世界恐慌の前触れ」 老後資金を失う人が続出する未来
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 年金だけで足りる?50代から始める「老後資金の育て方」
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- 最高難度のFP1級に合格! サバンナ・八木真澄さんが教える「世界一ゆるい勉強法」


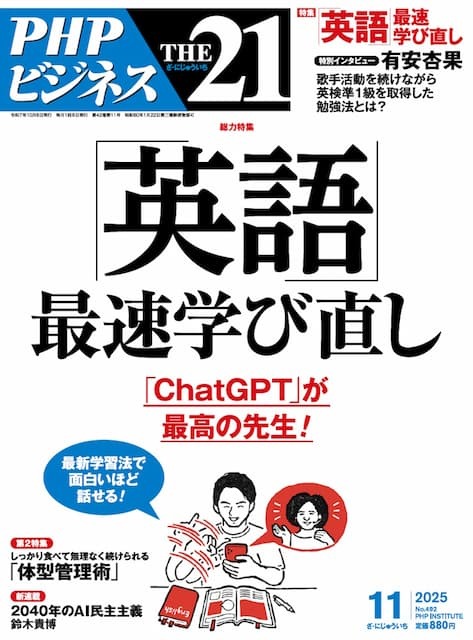

.jpg)


