年休取得がついに「義務化」。4月1日から休み方はこう変わった!
2019年04月02日 公開
2024年12月16日 更新
要注意!年休には「時効」がある
ドラマの中でよく使われる「時効」という言葉。実は年休にも「時効」があるのをご存知でしょうか。より正確には、年休には「消滅時効」というものがあり、労働者の年休請求権は、その権利が発生してから2年間有効ですが、2年を過ぎると消滅(失効)してしまうのです。
たとえば、入社し6カ月間継続勤務した従業員は、前述したように1年間に10日間の年休を取得できます。その後、1年経つと今度は11日の年休を取得できます。もし、それらをまったく使わなかったら、入社から2年6カ月を迎える直前の時点で、その人の年休は21日、ということになります。
そこに、今度は12日の年休が与えられるわけですが、年休は2年過ぎると消えてしまいますので、最初の年に与えられた10日間は、2年6カ月を超えた時点で消滅します。
つまり、年休は「10+11+12=33日」ではなく、「11+12=23日」ということです。
どんなに休まずに働いても、上限は6年6カ月以降に与えられる20日+20日の40日以上は増えない、ということです(もちろん、会社が自社の判断でそれ以上の年休を与えることは可能ですので、その場合は、この限りではありません)。
先ほど、日本人の年休の平均取得率は5割程度、というお話をしました。こうして取得されない年休は、2年ごとにどんどん消滅してしまっているわけです。
「休みたい社員」vs.「休ませたくない会社」
さて、この「年休を取る権利」ですが、労働基準法においては「労働者の請求する時季に与えなければならない」とされています。
つまり、年休をいつ取るかは原則、個人の自由。ただし、使用者には「請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」における「時季変更権」が認められています。これは、休みを取らせないのではなく、請求のあった日とは別の日に変更させる権利です。
ご想像のとおり、ここがトラブルになりがちなところではあります。すなわち、「休みたい」と「休まれては困る」のせめぎ合いです。
会社が「時季変更権」を行使できるのは、請求のあった日に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
では、何が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するのかについては、ひと言で言うのは難しいのが現実です。過去の判例でも、その会社の規模やその社員の業務内容などから客観的に判断すべきとなっています。
次のページ
会社が「休みを先延ばしさせることができるケース」とは? >
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月19日 00:05
- 止まらない円安にどう備える? 日本が再びハイパーインフレに陥る可能性
- 18時に帰る若手を横目に残業...「管理職の罰ゲーム化」が加速する日本の職場
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 「半日休んで何もしない」ことが管理職のビジネススキルになる理由
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- 「管理職にかかる過剰な負荷」は解消できるのか? 組織変革の要となる部門とは?
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- 西村知美さん「60代になったら...」 58の資格を取得してもまだ勉強を続けたい理由とは?
- 資格勉強の効率が劇的に上がる! 科学が証明した「最短で成果が出る勉強法」

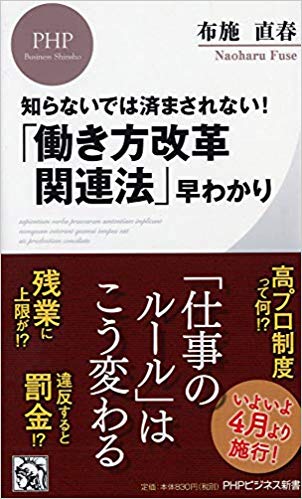


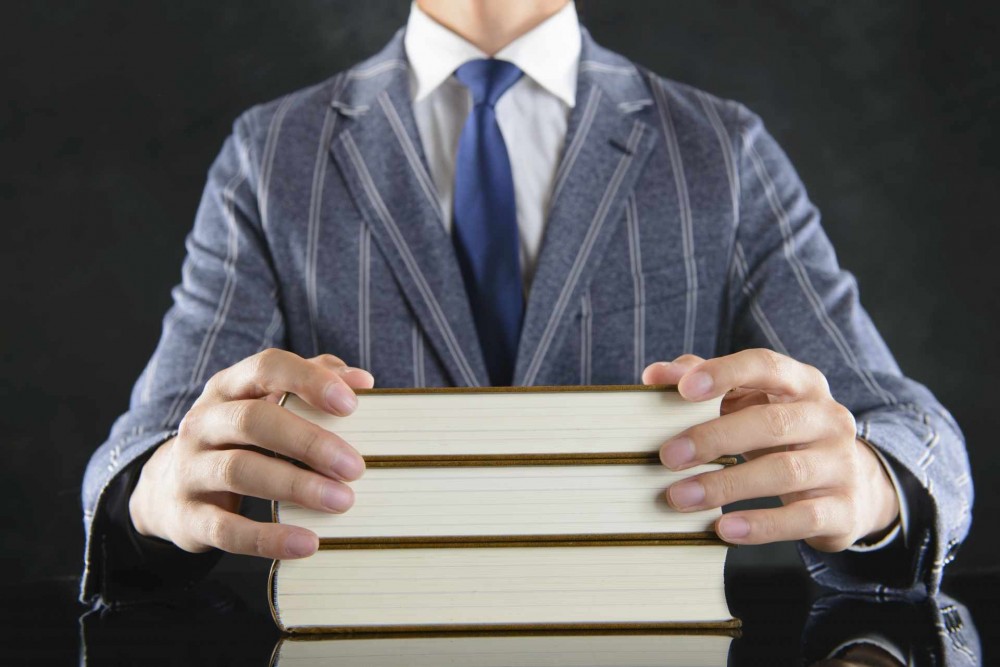
.jpg)

