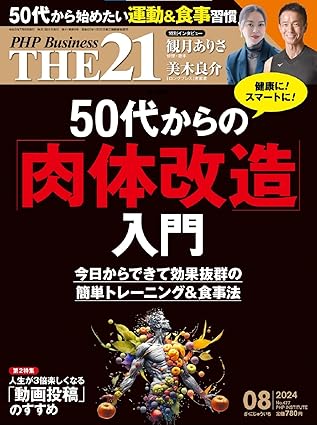モネが描いた『ルーアン大聖堂』は、なぜ非現実的な色彩をしているのか?
2025年01月10日 公開
2026年01月20日 更新

美術教師の末永幸歩です。このコラムでは、アート作品に向き合ったり、小さな子どもがみつめる世界に想いを馳せてみることで、物事を異なる角度からみつめ直し、自分だけの答えをつくる「アート思考」をしてゆきます。本稿ではクロード・モネの作品『ルーアン大聖堂』についてご紹介します。
※本稿は、『THE21』2024年8月号連載「ビジネスパーソンのためのアート思考トレーニング」より、内容を一部抜粋・再編集したものです。
なぜこの作品は非現実的な色彩をしているのか
蜃気楼にぼんやりと浮かぶかのような形、燃える炎のような色彩......。この作品には、想像上の世界や作者の感情が描き出されているのでしょうか?
そんな予想に反し、これはフランスのノルマンディー地方に実存する建築物がストレートに写生された作品です。題名も建築物の名称そのままに『ルーアン大聖堂』といいます。
作者であるクロード・モネは、この作品を制作した当時、この建物がよく見える真向かいのビルにアトリエを構えており、窓辺から見える実際の風景を目に映る通りに描きました。
とはいえ、実物の聖堂の色は、決して真っ赤ではありません。ヨーロッパの一般的な古い建築物と同様、グレーがかった色をしています。なぜ、実際の建物を見たままに描いたにもかかわらず、現実とはかけ離れたかのような色彩になってしまったのでしょうか。
意外と実感されていないことですが、質量や体積を伴った「色」という物質はこの世に存在しません。色は「存在するもの」ではなく、物体に光があたり反射した波長を視覚で受け止めることで、その人の脳内に「感じられるもの」です。
つまり、実物の大聖堂は「グレー」という固有の色を有しているわけではなく、移り変わる外光によって、見る人に一瞬ごとに異なる色味を感じさせるものであるはずです。
そこで、モネは「この建物は常にグレーだ」という思い込みを捨て去り、その瞬間の光の下で、自分の目に映る色をありのままに捉えました。それによって、従来の絵画以上に目に映る世界を正確に描き出そうとしたのです。
「毎日新しいものを発見しているのです」
一般的に「ありのままに対象を捉える」というとき、それは思い込みによって見失っていた対象の本当の姿をつかむことを意味します。しかし、モネがしていたのはそれとは異なる試みでした。
彼は、一連の作品の制作中に人に宛てた手紙に次のように綴っています。
「(制作が)まったく順調には進んでいません。なぜなら、毎日、前日には見たことのないものを発見しているからです」
実は、『ルーアン大聖堂』と題されたモネの作品は1つではなく、なんと33作品も存在します。モネは同じ建物を、約2年間にわたって描き続けました。
しかし、33枚のうち1枚として同じ色で描かれた作品はありません。
モネにとって「ありのままに対象を捉える」ということは、対象に一瞬ごとに新しい視線を注ぎ続けることであり、それによって対象の見え方を多重に増やしていくことだったのです。それは、対象の正体を明らかにするどころか、目を向けるたびに、対象の存在を不明瞭にしていくことでもあるのです。
立ちすくむ子どもの姿から 見えてきたこと
もうすぐ4歳になる娘は、この春から幼稚園に通い始めました。 朝、幼稚園に到着した子どもたちはすぐに園庭で遊び始めます。
しかし、娘は元気のない様子で入り口付近に立ちすくんだまま。「おいで、遊ぼう!」と先生に声をかけられても動こうとせず、一歩踏み出すまでにかなりの時間がかかってしまいます。 毎日こんな調子では困りものですので、どうにかして早く慣れさせなければと私は思い悩んでいました。
しかし、クロード・モネの「ありのままに見る」ことへの探究について思いを巡らせたとき、悩みの種であった娘の姿が違ったふうに感じられてきました。
目の前の状況に真正面から向き合い、自分の胸のざわめきを全身で感じ取っている瞬間......。それは、目の前の対象や自分自身の心に目を向け、ありのままに捉えている、まさにその瞬間なのかもしれないと思ったのです。
逆に考えると、私はいつの間にかあらゆる物事に対し、既存の知識や経験を当てはめ、その瞬間に実際に目の前で起こっている状況に視線を注いだり、自分の心の微妙な揺らぎを感じ取ったりすることが疎かになっていたような気がします。
戸惑い立ちすくむ姿こそ、娘がありのままに対象を捉えていることの現れなのだと考えれば、必ずしもその時間を短くしようと促したり、早く慣れさせようとする必要はないのかもしれません。
言うまでもなく、何もかもをありのままに捉えようとするのは現実的ではありません。 しかし、型にはまったものの見方で物事が単純明快になればなるほど、日常は平坦で味気ないものになってゆきます。
アーティストや子どもが対面している世界は、なんと拠り所がなく不確かで、しかし飽きさせることを知らないものなのだろうかと思います。
【末永幸歩(すえなが・ゆきほ)】
美術教師/アーティスト。武蔵野美術大学造形学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育)修了。アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を、都内の中学校や高等学校で展開してきた。子どもの創造性を育むワークショップ、大人向けアート思考セミナーなど、アートに関する活動を年間100回以上行なう。プライベートでは4歳児の子育て中。著書に22万部突破のベストセラーとなった『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)がある。
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月23日 00:05
- 止まらない円安にどう備える? 日本が再びハイパーインフレに陥る可能性
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 成功者はなぜ「ありがとう」を連呼するのか? 億万長者に学ぶ習慣の秘密
- 資格勉強の効率が劇的に上がる! 科学が証明した「最短で成果が出る勉強法」
- 「半日休んで何もしない」ことが管理職のビジネススキルになる理由
- 18時に帰る若手を横目に残業...「管理職の罰ゲーム化」が加速する日本の職場
- 西村知美さん「60代になったら...」 58の資格を取得してもまだ勉強を続けたい理由とは?