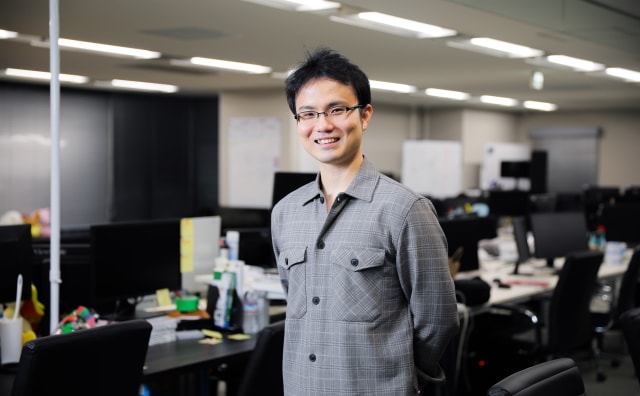オプトデジタル「LINEとのパートナーシップを強みに日本企業のDXを進める」
2020年12月25日 公開
2024年12月16日 更新

2020年7月、インターネット広告代理店大手の〔株〕オプトホールディングが、〔株〕デジタルホールディングスに社名変更した。企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する「デジタルシフト事業」を主事業として生まれ変わる決意の表れだ。これを実現するため、2020年4月に、グループ会社の〔株〕オプトの子会社として、新たに〔株〕オプトデジタルが設立された。その代表取締役に就任した野呂健太氏に、同社の強みや展望を聞く。
LINE社との強固なパートナーシップ
――企業のDXを支援すると言っても様々な形があると思います。御社はどのような形で支援をしているのでしょうか?
【野呂】DXはモノとなるサービスがなければ始まりません。そこで当社は、アジャイル開発に特化したシステムの受託開発と、LINEを活用した顧客接点変革のためのSaaSサービスの提供をしています。
受託開発の事例としては、損害保険ジャパン〔株〕(以下、損保ジャパン)のLINE公式アカウントを活用した、保険金請求をLINEで完結できたり、AIで事故車の修理費用の概算見積もりを自動的に算出できたりするサービスがあります。SOMPOひまわり生命保険〔株〕のLINEで給付金請求ができるシステムも、当社が手がけたものです。いずれも業界初のサービスです。現在は大手金融機関中心として支援をしていますがが、今後は業種を広げていきたいと考えています。
SaaSサービスは、自動車ディーラーや不動産会社、アパレル会社など、幅広い業種で、サービスの受付や顧客対応、オンライン商談などに活用していただいています。
――損保ジャパンの事例は、野呂代表が損保ジャパン(当時は損害保険ジャパン日本興亜〔株〕)に在籍していたときに立ち上げたものですね。
【野呂】そうです。オプトとのご縁は、私が損保ジャパンのDXサービス開発に携わっていたときに始まりました。当時のプロジェクトには、LINE〔株〕の開発パートナーであるオプトと、LINE社、損保ジャパンの3社で取り組んでいました。
当時のオプトのエンジニアは、非常に柔軟、かつ、スピード感を持って、サービスを作り上げてくれました。こんな組織があれば、他の企業、業界でも、もっとDXの波が起こせるのでは、と考えました。それが、オプトデジタル設立の背景です。私がクライアントのDX担当者の目線で見て、あったらいいと思う会社を形にした組織なのです。
私は代表を任されていますが、この会社の存在意義はあくまでクライアントのDXを実現するための手段なので、形にこだわりはありません。強いて言うなら、代表としての裁量をいただいているので、その辺りのやりやすさはあると思います。
――システムを受託開発する企業は多くありますが、御社の強みは何でしょうか?
【野呂】まず、LINE社との強固なパートナーシップです。LINE Biz Partner ProgramのTechnology Partnerとして、最上位のDiamondに認定されている企業は2社しかないのですが、そのうちの1社がオプトです。
オプトデジタルの設立と同じ2020年4月にはLINE Innovation Centerを設立し、当社のクライアントの要望をLINE社に伝え、LINE社からサービスとしてフィードバックしてもらうという座組みもできています。
LINEを活用した業界初のサービスを開発していることも、LINE社に高く評価していただいています。
もう1つ、開発のスピード感も強みです。特に金融機関のシステムには高いセキュリティが求められることもあって、システムを1つ作るのに年単位の期間がかかるのが常識なのですが、当社は2~3カ月で作ります。開発期間が短いということは、かかるコストも少なくて済みます。また、サービスを鮮度の良いまま世の中に出せるというメリットもあります。
この開発期間の短さは、大手金融機関のこれまでのシステム開発に対する固定概念を変化させることにつながったと考えています。これまではテキスト変更程度の修正でも2~3カ月かかると思っていたのに、エンドユーザー向けの本番のサービスをその期間で作ってしまうのですから。
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:03月01日 00:05
- 血圧を下げる「カリウムが豊富な食材」とは? 高血圧専門医が解説
- 高血圧専門医が教える「ほんの少しの意識」で降圧が優位に進む2つの秘策
- 医師が語る、40代からの健康診断で必ずチェックすべき「4つの数値」
- グラウンドワークス「エヴァンゲリオンの版権ビジネスが成功し続けている理由」
- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い
- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣
- 血圧を下げるには減塩だけでは不十分? 医師が語る「カリウム摂取」の重要性
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 「サッカーは世界一愛されている。日本で盛り上がらないわけがない」川淵三郎が貫いたJリーグへの信念
- 日本サッカーはなぜ「地域密着」なのか…23歳の川淵三郎が見たドイツの天然芝の衝撃