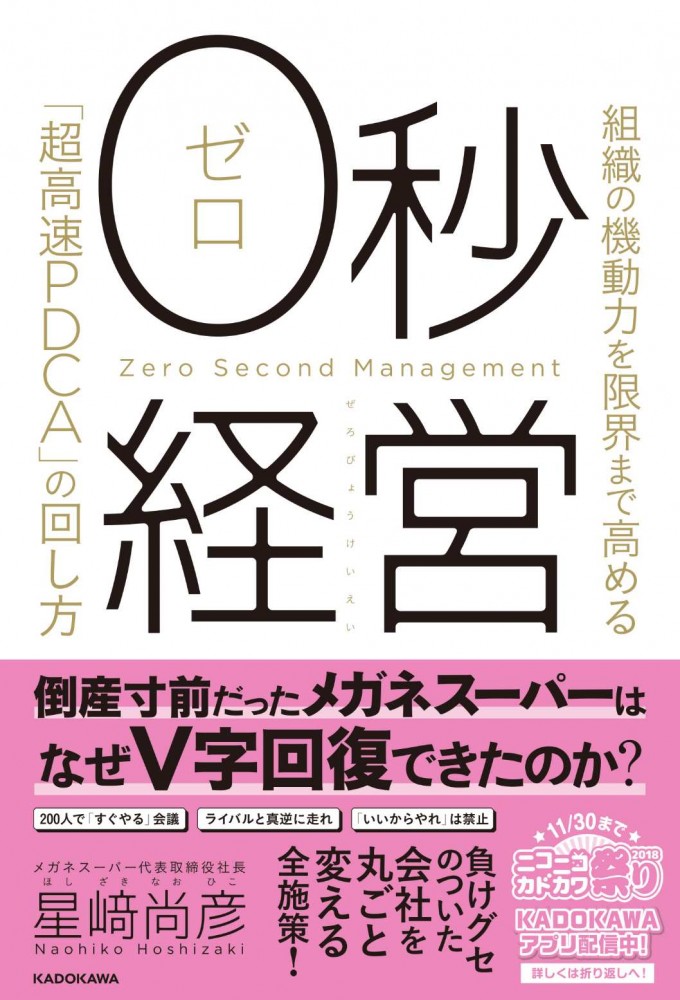V字回復社長が語る「MBAより大事なこと」
2018年10月11日 公開
2024年12月16日 更新
MBAは無意味ではないが、経営の役には立たない
バックグラウンドも多様だった。私も子供の頃、父の仕事の都合でイギリスに暮らしたことがある。だが、ここには、アルゼンチン人やスペイン人、ブラジル人がいる。アジア人も、ロシア人もいる。特殊部隊出身者が3人いたといえば、多様ぶりが伝わるだろうか。
ロシアの特殊部隊「スペツナズ」、イギリスの「SAS」、アメリカの「デルタフォース」から1人ずつである。要は皆、戦闘のスペシャリスト。戦地で部下を亡くした悲しみすら乗り越えて、マネジメントを学びにきていた。それにひきかえ自分はちっちぇえな、と思った。
天下の三井物産、世界を股にかける商社マンといえば聞こえはいいが、その実、完全にジャパニーズサラリーマンの考え方に染まりきっていた。どうやって組織のなかで出世するか、売上をあげるか、上司に好かれるか。それだけの人生を送っていたのだから。
とたんに、会社に戻るのがバカバカしくなった。クラスメイトたちも、「経営を学んだのだから、すぐ経営者になればいい」と屈託がない。まったくその通りなのである。
そんな経緯があるから、ビジネススクールでの経験が、私の生き方を変えた転機であるのは、間違いない。一方で、プロ経営者としてのイロハをビジネススクールで学んだかというと、まったくそんなことはない。どちらかといえば、ビジネススクールは、「特殊訓練」の印象が強いのだ。大量の課題、大量の予習と復習、それを異文化・異言語で、徹夜してでもやり切る。
毎日、ひたすら勉強ばかりだった。英語力やディベート能力は上がった。しかしビジネスについてはさっぱりである。経営者としては、だから完全な「叩き上げ系」だ。組織づくりもファイナンスも、ビジネススクールを卒業して日本に戻り、実際に社長業をしながら身につけた部分が大きい。
もちろん、理論はスクールでも学んだし、今でも座学を続けている。MBAという箔がなければ、社長としてのキャリアは開けなかったのも確かだ。しかし肝心なのは、座学で学んだことを、リアルなビジネスに落とし込むこと。そこで試行錯誤を経たものだけが、経営者のイロハとして血肉化する。
はっきりいって、MBAのケーススタディなんて、リアルビジネスで生きなかった。リアルビジネスは、よりダーティで、「清濁併せ吞む」どころか「濁濁濁併せ吞む」みたいな世界だ。ときおり背後から飛んでくる手裏剣をキャッチして投げ返す。そんな油断も隙もない日々のなかで、私は鍛えられていった。
不得手な分野には一切口を出すな
最初に社長を務めたのは、160年の歴史を持つスイスの宝飾企業、「フラー・ジャコー」の日本法人だ。ビジネススクールでの授業中に縁ができた。売上は全世界で30億円、うち15億円が日本法人。その日本法人の経営課題を解決しろという。私は「日本法人の経営は日本人に任せるべき」とプレゼンした。それを当のフラー・ジャコーの経営陣が目に止めた。
「ホシ、お前がやってくれ」。当時34歳のことである。リスクを数え上げれば、いくらでもありそうに思えた。売上15億円は、三井物産とは比較にならない規模である。「これだと家のローンも組めないかな」などと思いつつ、当時、日本の企業では34歳を社長にすることは想像できなかったので、これを千載一遇のチャンスと捉え快諾することにした。これが、プロ経営者としてのキャリアのスタートになる。
会社を渡り歩くプロ経営者の宿命として、どこにいっても最初は業界の素人だ。フラー・ジャコーはスイスの宝飾企業だし、その次はイタリアの靴メーカー「ブルーノマリ」。その次はアメリカのスノーボードブランド「バートン」。業界はバラバラである。
しかし、経営のプロであれば、どんな業界でも「経営はできる」というのが私の持論だ。業界の素人であることは、何のマイナスにもならないどころか、むしろ既成概念に縛られないのでプラスだと考えている。
メガネスーパーに来る直前は、109系アパレルブランド「クレッジ」の経営再建に携わっていた。ファッションには昔から縁がなかった。自分にセンスがないことも承知していた。三井物産新人時代、先輩に連れられて行った日比谷のラジオシティというディスコでは「君、ダサいからダメ」と入店で弾かれた。見かねた先輩に「これを買え」といわれた服をぜんぶ揃えたぐらいである。
だから、クレッジの社長に就任しても、ファッションについて専門性の高いことには一切口を出さなかった。ただし、経済合理性がない、ロジックの追究が甘いといった違和感があれば、逃さず指摘する。これはメガネ屋になっても同じことだ。
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:02月14日 00:05
- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- 介護保険では1時間以上のケアは困難という現実...... ある起業家が立ち上がった理由
- なぜ50代から「すごい人」より「いい人」を目指べき? 年代で変わる生き方戦略
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 止まらない円安にどう備える? 日本が再びハイパーインフレに陥る可能性
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- 西村知美さん「60代になったら...」 58の資格を取得してもまだ勉強を続けたい理由とは?
- 言語化力はどうすれば身につく? 小学校の日記教育が示す「自分と対話する」重要性