依頼に応えるだけの仕事への疑問…世界的デザイナーは「組織と自分」をどう考えたか
2021年05月24日 公開
2024年12月16日 更新
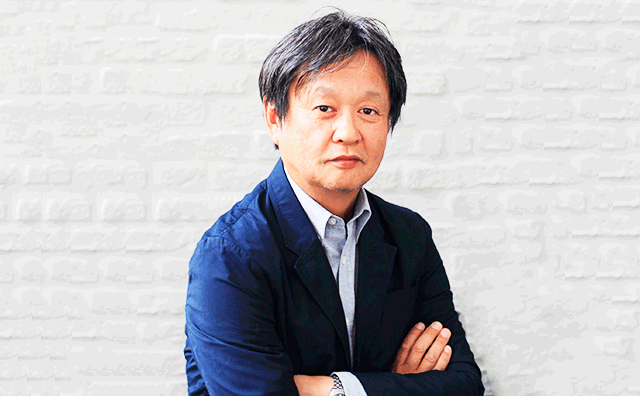
au/KDDIの携帯電話「INFOBAR」や無印良品の「壁掛式CDプレーヤー」など、多数の作品やブランドを手がけ、アームチェア「HIROSHIMA」が米国アップル社に大量採用されたことも話題となった深澤直人氏。そのデザインを生んだ転機とは?(取材・構成:塚田有香)
※本稿は『THE21』2021年5月号より一部抜粋・編集したものです。
米国で評価された「日本のキャリア」
プロダクトデザイナーとしての自分のキャリアを振り返ると、大きく三つの段階に分かれます。第1段階は、美大卒業後に就職した日本の電子機器メーカーで、企業に所属しながら働いた時期。ここで産業デザインの基本を実践で学びました。
第2段階は米国に渡り、デザインコンサルティング会社で仕事をした時期です。デザインの概念は海外から入ってきたものですから、自分もその本場でやってみたい。30代を迎える頃に、その思いが強くなりました。
世界で名を知られたいくつかのデザイン会社に、自分の作品をまとめたポートフォリオを持ち込み、カリフォルニアにあるデザインコンサルティング会社ID Two(現・IDEO)に入社が決まりました。
現在では「デザイン思考」を世に広めた会社として知られますが、私が入社したのは創業から間もない頃。米国ではシリコンバレー発の産業が急成長を遂げていて、次々とIT関連の仕事が舞い込みました。
ここで思いがけず、私の日本時代のキャリアが高く評価されました。メーカー時代に様々なデジタル製品の開発に携わり、中にはスマートフォンの原型とも言えるデバイスをデザインしたこともあったのですが、シリコンバレーの人たちにそれらを見せたところ、「これまでにない新しいインターフェースだ!」とびっくりされたのです。
私は相手の胸を借りるつもりで海外へ出て行ったのですが、意外にも「最先端のハイテク製品のデザインができる日本人が来た」と思ってくれたようです。
米国で約7年間を過ごしたあと、40歳で帰国してIDEO東京支社を立ち上げ、会社を経営しながら、デザインコンサルティングを日本で広めました。これがキャリアの第3段階です。
47歳で独立してからは、米国だけでなく欧州からの依頼も増え、テクノロジー製品に加えて、家具や食器など、伝統工芸的な製品のデザインを手がける機会も増えました。
主観を排し普遍を導く「客観写生」
自分のターニング・ポイントはいつだったかと考えると、米国にいた30代半ばが大きな転機だったように思います。それまで私は、企業内デザイナーやデザインコンサルタントとして、会社や顧客からの依頼に応えてきました。
1980年代は、刺激的で見る人の高揚感を煽る「エモーショナル・デザイン」が世界の潮流で、私も若い頃はそんなデザインをしてみたいと思っていましたが、組織の一員である以上、アーティストのように自由に自己表現するのは難しい。
「誰かの依頼に応え続けるだけでいいのか」と迷い始めたとき、出会ったのが「客観写生」という言葉でした。
これは高浜虚子の『俳句への道』(岩波文庫)にある言葉で、そこには「単純に似たる客観の描写のうちに図らずも作者の深い複雑な主観を捉え得たときは、読者はそれから深い感銘を得るのである」と書かれていました。それを読んで、デザインも同じではないかと、ハッとしたのです。
デザイナーが自分自身を表現し、個性や感情を発信することが必ずしも人々の共感を呼ぶとは限らない。むしろデザイナーは主観を消し、生活の中の何気ない現象や情景に客観的な視線を向けるべきではないか。
共感とは特殊なものではなく、すべての人が無意識のうちに感じている喜びや違和感といった「普遍」から導き出せるものだ。つまり、「私はこう思う」ではなく、「きっと、皆、こうだよね」というものを日常の中から写し取れば、それが人々の共感を呼ぶデザインになる。
それに気づいてからは、アイデアが無限に湧くようになりました。人間が本質的にシェアしている共通概念や暗黙知のようなものを「客観写生」すれば、顧客から発注される「より使いやすく」「もっと売れるように」といった条件や前提を超えて、自ずと世の中が求めるデザインになるからです。
特に私が注目するのは「違和感」です。ある商品がSNS上で話題になっていて、周囲も「いいね」と言うけれども、心のどこかで「本当かな?」「何か、おかしくない?」と引っかかる。そんなときは、実は他の人たちも口では「いいね」と言いつつ、同じように違和感を覚えているものです。
この皆に共通する違和感を見つけて、人々が気づかないうちにそっと取り除くのが私の仕事。すると「何か、よくなったね」と喜んでくれます。例えば無印良品の壁掛式CDプレーヤーも、違和感を取り除いたことで生まれたデザインです。
従来のオーディオ製品は、黒い箱を積み重ねた重厚な造形が当たり前でした。そこへ、白くて薄くて、換気扇のように紐を引っ張るとCDが回り出すデザインを提案しました。
最初は驚かれましたが使ってみると皆が「こういうのもいいね」と思ってくれた。常識とされていたものに潜む違和感を取り除き、「でも本当はこんなのもいいと思っていません?」と示したことで、共感を得たのです。
人々の「普遍」に届いたこの製品は、移り変わりの激しい電気製品にしては珍しく、十数年売れ続けるロングセラーになりました。
THE21の詳細情報
アクセスランキング(週間)
更新:01月23日 00:05
- 止まらない円安にどう備える? 日本が再びハイパーインフレに陥る可能性
- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック
- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」
- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」
- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方
- 成功者はなぜ「ありがとう」を連呼するのか? 億万長者に学ぶ習慣の秘密
- 資格勉強の効率が劇的に上がる! 科学が証明した「最短で成果が出る勉強法」
- 「半日休んで何もしない」ことが管理職のビジネススキルになる理由
- 18時に帰る若手を横目に残業...「管理職の罰ゲーム化」が加速する日本の職場
- 西村知美さん「60代になったら...」 58の資格を取得してもまだ勉強を続けたい理由とは?



